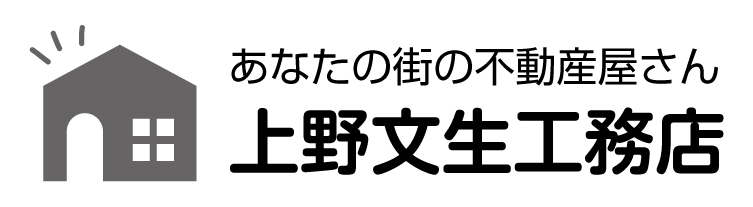ご売却までの流れ
STEP
02
現地確認、査定
当社の営業エリア内であれば、ご指定の場所までお伺いさせていただきます。売主様立会いのもと建物や土地の状況を見させていただいた上で、売主様の希望を取り入れながら売却価格を決めさせていただきます。

STEP
03
媒介契約、仲介
売却価格が決まりましたら、お客様と当社とで媒介契約をむすびます。

STEP
04
購入者探し、現地案内
当社に物件の売却を依頼していただいた情報は当社のホームページ又は看板、新聞折込チラシなど積極的に営業させていただきます。購入希望者が見つかりましたら、売主様にご連絡させていただきます。

STEP
05
売買契約
売主、買主双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。売買契約書が締結しましたら、契約書の記載内容にもとづいて権利や義務を履行することになります。

STEP
06
物件引渡し
残代金の受け渡しと、物件の引渡しは同時におこないます。
※売買後は当該物件の情報は直ちに当サイトより削除致します。

ご購入の流れ
STEP
01
ご相談・条件整理
希望エリア・予算・物件タイプなどを確認。資金計画やローンの事前相談も行います。

STEP
02
物件探し・ご紹介
条件に合う土地や建物をご提案。実際に現地見学や内覧をしていただきます。

STEP
03
購入申込(買付け)
購入希望の物件が決まったら、売主に「購入したい」という意思を正式に伝えます。

STEP
04
重要事項説明・売買契約
物件や契約内容についてご説明。内容にご納得いただいた上で契約を締結します。

STEP
05
住宅ローン本申込み・審査
ローンを利用する場合は金融機関へ申込。承認後に契約を進めます。

STEP
06
残代金決済・引渡し
売主へ代金を支払い、鍵や登記手続きを行い物件を引き渡し。

不動産用語のご説明
一般媒介契約
一般媒介契約とは依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を依頼することができる契約です。このうち他の宅地建物取引業者を明らかにする義務のあるものを「明示型」といい、明らかにする義務のない「非明示型」の2種類があります。
依頼者及び業者が見つけた相手方と取引が成立した場合は、依頼した他の宅地建物取引業者に報告しなければなりません。
専任媒介契約
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を禁ずる形式です。又、依頼者自ら見つけた相手方と売買又は交換の契約をすることができます。
専属専任媒介契約
依頼者が媒介や代理を依頼できる宅地建物取引業者は1業者のみで、依頼者が見つけた相手方でも、依頼した宅地建物取引業者を通じて契約を結ばなければなりません。
それは、どのような場合でも、売買契約が成り立てば宅地建物取引業者は報酬を得られるため、積極的な営業ができます。
又、宅地建物取引業者は、目的物件を大臣が指定する指定流通機構(レインズ)に専属選任媒介契約の締結の日から3日以内に登録しなければなりません。
又、専属選任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、1週間に1回以上業務の処理状況を依頼者に報告しなければなりません。
重要事項説明書
宅地・建物の売買契約を行う場合は、宅地建物取引士の資格を持った者が取引主任者証を提示して、物件と取引について重要事項を書面をもって説明しなければなりません。
これを重要事項の説明といいます。
重要事項説明書には、不動産取引の最も重要なことが書かれています。面倒くさがらず、書かれていることについて、納得がいくまで、説明を求めることにしましょう。
税金
不動産を売却した時の税金は、居住用、事業用、遊休地、それから所有期間等によりますが、税理士といっしょに、節税対策も含めアドバイスさせていただきます。
リフォーム(中古住宅)
見映えがいいように売主がリフォームしても、買主の好みに合わなければせっかくお金をかけて工事をしても無駄になってしまうので基本的には、買主が物件の引渡しを受けた後、工事を行うのが一般的です。
地目
地目とは、その土地の利用状況を表した区分のことで、宅地、田、畑、原野、山林、雑種地など、全部で21種類に分かれています。
ただし、現代宅地として利用されていても、登記簿上は畑や山林などのままになっているなど、登記簿と現況が一致しないことが多くあります。
又、地目が農地になっていれば、農地以外のものにするには農地法第5条(都道府県知事)の許可を受けなければなりません。
農業委員会
農業委員会とは、農業委員会等に関する法律に基づいて、原則として一市町村に一つ設置される委員会。
農地法や土地改良法等に基づき、農地等の利用関係の調整や自作農の創設維持、農地等の交換分合などの事務を処理します。
分譲宅地
一団の土地を複数の区画に区分けして、その区画ごとに売買し、または、借地権を設定、若しくは移転する住宅用地をいいます。
境界
契約する前に売買対象地と官有地を含む全ての隣接する土地の境界について、当該所有者の立会いの下に境界確認を行い、これに基づく測量図に署名、押印(実印)し、印鑑証明書が添付された状態を、「境界が確定している状態」という。
このようにして作成された測量図を「確定測量図」といい、原則として分筆、合筆、地積更正登記が可能です。
実測図がない等隣地との境界が不明な場合には、隣地所有者との間で土地家屋調査士や測量士等の専門家も交えて境界を定め、境界確認書を作成することです。
登記簿によって判明しない権利
(1)占有権・・・占有権とは物を占有しているだけで認められる権利です。登記する制度も在りませんし、取得時効及び消滅時効もありません。物を占有している状態ー事実上支配している状態ーを物権として保護しないと、社会の平穏が保てないからです。
(2)入会権・・・入会権とは、たとえば、その土地に住む人が山に入ってマツタケや山菜、あるいは木を伐採する権利を入会権という。
(3)留置権・・・留置権とは、他人の所有物に関する債権を持っている人が、保全のためにそれを所有(占有)しているときに、債務者から弁済を受けるまで対象物を自分の支配下に置く権利のことです。
その他、登記されない権利として、水利権、農地法による電気事業者の電線路施設の地役権、無地番地の権利、相隣関係上の通行権、などがあります。
徒歩何分という計算の仕方
道路距離を測り80mを1分で計算しています。1分未満の端数は、切り上げて、1分と計算して表示しています。
仲介手数料
宅地建物取引業者が、売主と買主の仲介を行い、売買契約を成立させるのが仲介(媒介)です。
この場合売買契約を結ぶのは、あくまでも売主と買主であり、その仲介を行った宅地建物取引業者には、仲介手数料を支払うことになります。
この手数料の金額は、法律によりその上限が定められています。
その金額は、最大で売買代金の3%プラス6万円となります。2024年6月21日の改正後、物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円(税抜)となりました。
中古住宅
中古住宅を購入する場合は、築年数はその家の痛み具合のある程度の判断基準になります。
又、築年数が浅い物件でもずっと人が住んでいなかったり、管理が悪い場合は、痛みが激しいこともあります。
しかし、古民家などの古い物件でも、手入れが行き届いていたり、定期的にリフォームをしている場合は、痛みが少ないケースもありますが、購入する前に、問題がないか建築関係の専門家に相談するのがよいでしょう。
(1)建物にシロアリの被害がないか?土台や、柱、小屋組み、などよく調べることが大切です。
(2)雨漏れがしていないか?小さな雨漏りからも放っておくとシロアリは発生します。
押入れの天井の隅や、浴室の天井の上からも雨漏れしていることもあります。
(3)基礎にひび割れが入っていないか?基礎に大きなひび割れが入っていると、建物が傾いていることもあります。
(4)人によりますが、気になる方はその建物について家相も調べておくと安心です。
トイレ、浴室、池、神仏等が鬼門の方角に入っていないかも調べることも大切なことだと思います。
署名と記名押印
署名(サイン)とは、自分の名前を自筆で書くことであり、自分の氏名を自署以外の方法で記載することを記名といいます。
従ってゴム印、ワープロ印字、他人による署名でもよく、さらに記載された氏名の後に印鑑を押すことを記名押印といいます。
わが国では、署名より記名押印を重要視する傾向にあり、押印のない単なる署名よりも記名押印のほうがベターとされています。
一方、法律上は署名と記名押印は同等の効力を持つとされているものの、民事裁判などの場合、記名押印のある文書にはより強い証拠力が認められています。
公租公課の起算
公租公課とは、固定資産税、都市計画税など土地建物に課される税金のことです。
固定資産税、都市計画税は、1月1日現在、固定資産課税台帳に登録された登記名義人に対し、市区町村が課する地方税でその年の4月依頼に納付書が送付されます。
年の途中で売買がされた場合、所有者が変わることになるので、負担区分を明確に決めて精算する必要があります。
通常は、目的物件の引渡し日を基準として区分し、引渡し日の前日までの期間は売主の負担、引渡し日以降は買主の負担とすることが多いです。
公簿売買と実測売買
不動産の契約には公簿売買と実測売買があります。
公簿売買は公簿面積(権利書に載っている面積)と実際の面積が一致しないことがあっても精算しないことを決めた契約です。
別荘地、山林、農地、など売買金額に比べて測量費用が高すぎるとか、取引を急ぐ場合、あるいは、既分譲地、区画整理済等で登記簿面積が信頼できると判断した場合に採用する手法です。
実測売買は、本来の方式は契約締結時までに土地の実測面積を確定し、それに基づいた売買代金によって契約し、決済するものです。